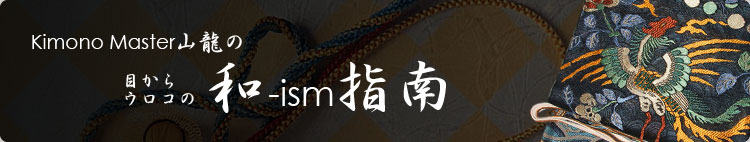

Kimono Master 山龍
|
|

帯は約4m40cmと長いので、二つ折りにしました。下(左側)から、「たれ紋」「合い紋」「裏太古」「太古」。太古の鳳凰(通称ギャオス)以外は、花の柄です。

「太古」の次にくるのが「腹紋」、その後の無地の長い部分が、身体に巻き付ける部分です。そしていちばん上(右側)に「果て紋」。どちらも、左右どちら巻きに締めてもいいように、柄が上下で逆さに入っています。
|
次が「裏太古(うらだいこ)」と言って、二重太鼓を締めたときに、太古の裏側にちゃんと見えるように、わざわざ柄をひっくり返して折り込んである、これまた贅沢なもの。そして、いちばんの花形の「太古」の柄がやっとくる。
「太古」の柄の次が「腹紋」。締めたときにお腹の部分に出る柄である。それからぐるぐるとお腹に巻く無地の部分が続き、最後のてさきの部分にくるのが「果て紋」。私の帯の場合は、「腹紋」と「果て紋」が、同じ柄を逆向きで折り込んである。帯を左右どちら巻きにしても、柄が出るようにだ。もちろん、ここにそれぞれ違う柄が入った帯もある。
「ただ、こんな帯探したら、高いもんばっかりになってしまうさかいに、オススメは「太古柄」言うて、太古と腹紋が入った帯やな」
山龍に言わせれば、腹紋以外、脇腹の部分が無地の帯が、締めたときに着姿がかっこよく見えるのだそうだ。
「全体に柄が入っている帯は、一見豪華やけど、締めたときに太って見えるで。締めたときにかっこよく見える帯が、エエ帯や」
背中の柄に守られて……
そもそも「二重太古」や「一重太古」という太古を作る帯の締め方は、江戸時代の中期に花街の太夫さんが「前太古」というのをお腹のところで締めたのが始まりだそうだ。当時の太夫さんと言えば、ファッションリーダー的存在。「みんな真似してお太古を締めるようになったんやけど、普通の人が前で帯を締めたら生活できへんから、背中に回しただけ」
そして、太古をかっこよく作るための帯枕ができ、それを隠す帯揚げができ、畳んだ帯を締める帯締めが道具として必要となったというわけ。
また、本来帯の柄付けに意味があるように、帯の柄そのものにも意味があるという。
「腹紋いう、帯を締めたときに腹の部分にくる柄は、相手に対する敬意を表す柄。背中の太古の柄は、自分自身を守る意味の柄なんよ。だから、腹紋とお太古の柄が同じいうのはおかしいねん」
な〜るほど! 私の場合は、花で相手に敬意を表し、鳳凰すなわちギャオスに守られているというわけか。極道の姉さんが、背中に唐獅子牡丹を彫るみたいな気分……とは違うと思うけど、ちょっと心強い気がしてきた。
ついでに言うと、腹の部分に見える帯の長方形は、神事に於ける祝儀袋に例えて、祝儀袋に書かれた「寿」の文字に当たるのが腹紋、水引にあたるのが帯締めなのだとか。「寿」の思いが外に出ないように水引が結んであるように、腹紋の柄の意味が外に出ないように、組紐を結ぶというわけだ。祝儀袋の「寿」の文字は袋のど真ん中にはないから、腹紋も中心から外して締めるのが正しく、しかもカッコイイと山龍は言う。
「ま、かっこよければそんなことどうでもエエんやけど、そういう意味ぐらい知ってたほうがエエんちゃうかなと」
ちなみに、最近の帯のメーカーのほとんどに知識がないから、そういう理にかなった帯は、今では少ないそうだ。確かにファッションとして考えた場合、相手への敬意だとか、自分を守るだとか、水引だとかはどうでもいいことだと思う。しかし、柄にそういう意味を持たせた日本の文化や思想は、着物を装う時の心の豊かさにつながるような気がする。知っていると、背筋がしゃんと伸びてくるような……。いずれにせよ、着物にも増して、帯の需要制を再認識させられた。
「帯の幅もな、普通は8寸(約30cm)やから、腹の部分は半分の4寸。これはだいたい155cmの身長の人にあったバランスなんよ。でも、今はみんな背が高くなったやろ。165cmの人やったら、この幅やと、伊達締めみたいに見えて格好悪い」
その場合は、真っ二つに折るのではなく、6:4、身長170cmだったら、7:3ぐらいに折って、幅の広いほうを表に出せばいいそうだ。
お座敷衣裳だった昔と違い、今の着物は立ち姿で見せる。ゆえに着物とのバランスの問題というわけだ。
ちなみに私は、155cmという古風な身の丈なので、何の問題もない。嬉しいような、悲しいような……。せっかくいいい話聞いたのに、背中のギャオスが泣いてるぜ!
(2008.5.15)