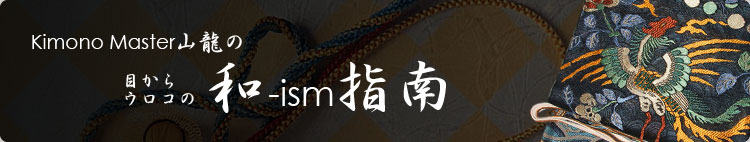

Kimono Master 山龍
|
|

待つこと5か月! でやっと上がってきた襦袢。どうです? カッコイイでしょう! 袖口からチラリと見える感じも素敵。
|
「ああ、今、作ってると思うよ(笑)」
と上ずった声で言った後、さすがに山龍も慌てたのか、
「あの襦袢はカッコええで〜! 着物みたいな襦袢やで」
「こんな襦袢着てる奴、他におらへんよ〜」
「そのまま出かけられるような襦袢やで」
と、立て続けにその素晴らしさを並べ始めた。そんなのどうでもいいから、早く作らんか〜い!
さらに待つこと1か月。2月の末にやっと……ホントにやっと、待ちに待った襦袢が仕立て上がって来たのだが、新たな悲劇が私を襲う。着てみたら、ちょっとサイズが大きいではないか。仕立て直しである。怒りを通り過ぎて、悲しみと絶望が私を包んだ。ああ、この襦袢は私の手元には一生届かないのだわ……。私、待〜つ〜わ、いつまでも、待〜つ〜わ……あみんの懐かしのヒット曲「待つわ」が頭の中に鳴り響く……。
そして、怒りも、悲しみも絶望も忘れたついこの間、やっと届きましたよ、山龍のこだわりの襦袢が!
男物の生地だという柄は、山龍のいうとおり、メチャメチャかっこよかった。ピンクや黄色のぴらぴらした花柄でないところが私の好みにピッタリである。こんな素敵な襦袢もあるんだ! というのが正直な感想だ。スーツでも、生地や仕立てがメンズライクなほうが絶対に上質でカッコイイが、着物もそこは同じ。常日頃から、着物の生地にしても、襦袢の生地にしても、そそられるものは男物が多い。そこを見抜いた山龍はさすがである。
待った甲斐はあった。待ち遠しい気持ちが熟成している分、喜びもひとしおである。ま、もう少し遅かったら、熟成しすぎて発酵してしまい、「もういらん!」ぐらいいってたかもしれませんが……。
花開いた襦袢文化
「襦袢も、凝りだしたら、着物と同じぐらい凝れるねん」と、山龍はいう。結納のときに着る振り袖の襦袢は、友禅の総柄だったり、中には総絞りの襦袢もあるのだとか。そこまでいくと、価格も20万円〜25万円というから驚きだ。生地が着物の生地に比べて薄く、内側を滑りがいいように織ってある以外は、着物の作り方とほとんど変わらない考え方なのである。襦袢を侮るべからず、である。
そもそも襦袢にいろいろな柄を入れだしたのは、江戸時代に徳川幕府が一般庶民の贅沢を禁止する『奢侈禁止令(しゃしきんしれい)』を出した頃からだそうだ。柄の入った豪華な着物は、徳川御三家以外着てはならず、庶民は質素倹約、無地など地味なモノしか着ていけないという贅沢禁止令である。そんなこといわれても、おしゃれはしたい! と思った江戸の町人達は、それなら下着である襦袢に柄を入れてしまえ……ということで、絞りの柄や花柄の小紋を型染めで入れたのが始まりだとか。
「でな、当時の浮世絵とか見るとわかるけど、みんなほとんど襦袢で暮らしてはったんよ。帯もしてへん。腰ひもなんよ」
山龍にいわれて改めで江戸時代の庶民を描いた絵を見ると、今までは着物だと思っていたけれど、確かに男も女も襦袢姿である。腰ひも1本で結んで、肌も露わ。あらまあ! 花街の女性に至っては、裾を引きづり帯を前で締め、片肌脱いでのベアトップ状態。なんとも自由な! 男も、粋な柄の着物だなあと思えるモノは、みんな襦袢である。
「時代劇で、丹下左膳が般若の柄とか着とるやろ。あれも襦袢やで」
当時、デザイン的に面白いと思えるものは、全て襦袢だったというわけである。ちなみに、江戸の粋は“縞”と“格子”などといわれて、縞柄や格子柄の着物を羽織った浮世絵があるが、これも着物ではなく、寒さを凌ぐための丹前みたいなものが多かったとか。襦袢の上に丹前! 結構いい加減だったんですね、江戸時代って。
しかし、当時こんなに花開いた襦袢文化があったのに、今私たちがイメージする女物の襦袢といえば、ピンクの無地や淡い花柄ばかりなのはなぜだろう? 着付けの本を見ても、出てくるのはそんなものしかない。
「そりゃあ、着物が売れへんのに、凝った襦袢作ったかて売れんから。でも、お願いやから、ホンマにピンクの襦袢はやめて!……と書いといて(笑)」
これは、山龍師匠の絞りの襦袢。染め分けがしてあり、三度笠をかぶった飛脚が絞ってあるという凝ったもの。男物の襦袢って、かなり素敵なものが多いです。

これは、山龍師匠の絞りの襦袢。染め分けがしてあり、三度笠をかぶった飛脚が絞ってあるという凝ったもの。男物の襦袢って、かなり素敵なものが多いです。
|
カッコイイ襦袢を見つけるには、男物の着物のレパートリーが広い呉服屋さんを探すといいという。男物の着物は、女物ほど華やかさやバリエーションがない分、裏もの(裏地や襦袢)を凝らなければならないという意識がある。そのため、女性用の襦袢も、凝ったものが揃えてあるそうなのだ。
「男もんを扱い慣れてない呉服屋は、襦袢はただの下着くらいにしか思うてへん」
買う側の私たちも、襦袢はただの下着ではなく、違いのわかる女の証であるということを、きちんと認識していなければいけないということだろう。それにしても、袖口や袂(たもと)から覗くだけなのに、贅沢な話である。
「確かに自己満足やな。ただ、脱いだ後の、体の微妙なぬくもりを感じるような襦袢が掛けてあると、何ともいえない色っぽさを感じる……のは、僕だけやろかあ?」
ドキッ! 着物姿に滲み出る女の色気とセクシー度数を、もう少し勉強し直さなければ!
(2007.5.16)